「投資信託」と「ETF」なんとなく似ているようで、実はまったく違うもの。
まず結論からお伝えすると、
初心者には「投資信託」がおすすめ!
理由は、投資に時間や知識がそこまでなくても、積立設定すれば自動で投資され、
資産が増えるから。
とはいえ、ETFにも魅力はある。
それぞれの特徴をしっかり押さえて、自分に合った投資を選んでいこう。
投資信託とETFの違い

| 項 目 | 投資信託 | ETF(上場投資信託) |
|---|---|---|
| 売買 | 1日1回の基準価格 | 市場でリアルタイムの価格 |
| 価格 | 100円から買える (ネット証券) |
数千~数万円などまとまった資金が必要 |
| 配当 | 基本は自動で再投資される (課税なし) |
配当金として受け取れるが課税対象 (約20%) |
| 手数料 | 信託報酬がかかるが売買手数料は 無料のことが多い |
信託報酬+売買手数料がかかることがある |
投資信託のメリットとデメリット

・メリット
-
100円から購入できる(ネット証券の場合)
-
積立設定で「自動で投資」ができる
-
ニーサを活用すれば、利益が非課税
-
運用のプロが管理してくれる
・デメリット
-
基準価額は1日1回しか決まらないため、リアルタイム性がない
-
信託報酬(運用コスト)がかかる
ETFのメリットとデメリット
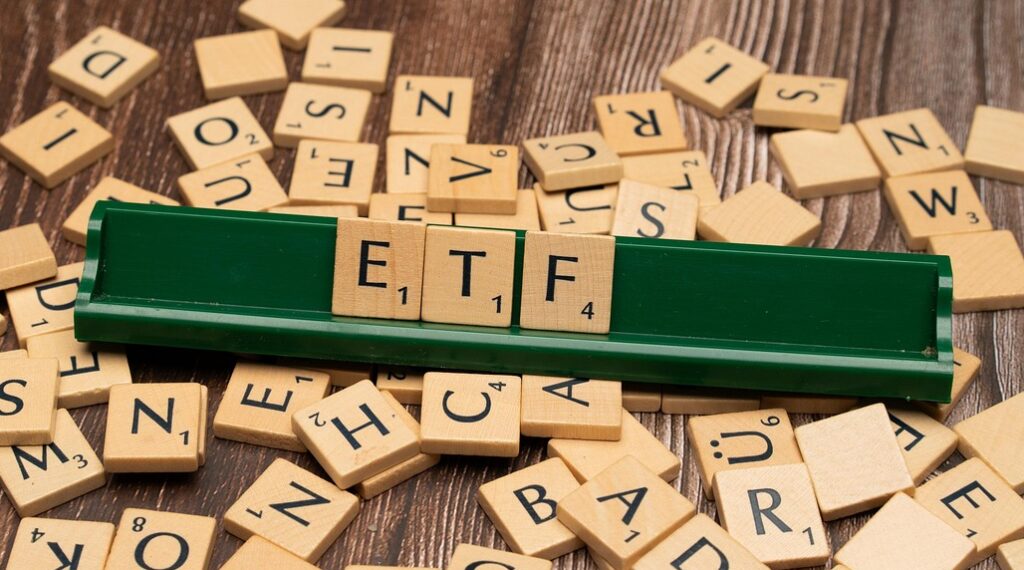
・メリット
-
株と同じようにリアルタイムで売買できる
-
配当金を受け取れる
-
信託報酬が低めな商品が多い
・デメリット
-
配当金には約20%の税金がかかる(確定申告で控除できる場合も)
-
積立設定など自動化はしにくい
-
初心者にはややハードルが高い(ある程度の資金が必要なのと、買うタイミングを図ること)
おすすめの投資信託 3選(楽天証券・SBI証券で購入可能)

① eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
-
特徴:全世界の株式に分散投資できるインデックスファンド
-
メリット:これ1本で先進国から新興国まで幅広くカバー
-
購入可能:楽天証券、SBI証券の両方で購入可能
② eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
-
特徴:米国の代表的な500社に投資するインデックスファンド
-
メリット:米国経済の成長を取り込むことができる
-
購入可能:楽天証券、SBI証券の両方で購入可能
③ 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
-
特徴:米国のほぼすべての上場企業に投資するインデックスファンド
-
メリット:米国市場全体の成長を取り込むことができる
-
購入可能:楽天証券で購入可能
おすすめのETF 3選(楽天証券・SBI証券で購入可能)

① iShares Core S&P 500 ETF(IVV)
-
特徴:米国のS&P500指数に連動するETF
-
メリット:米国の大型株に分散投資が可能
-
購入可能:楽天証券、SBI証券の両方で購入可能
② Vanguard Total Stock Market ETF(VTI)
-
特徴:米国のほぼすべての上場企業に投資するETF
-
メリット:米国市場全体の成長を取り込むことができる
-
購入可能:楽天証券、SBI証券の両方で購入可能
③ NEXT FUNDS 日経平均株価連動型上場投信(1321)
-
特徴:日本の代表的な株価指数である日経平均株価に連動するETF
-
メリット:日本の主要企業に分散投資が可能
-
購入可能:楽天証券、SBI証券の両方で購入可能
積立投資を始めた年齢別シミュレーション(年利4%、月3万円積立)

以下は、積立投資を始めた年齢別に、65歳まで月3万円を年利4%で積み立てた場合のシミュレーション。
| 開始年齢 | 元本(積立額) | 最終積立額(65歳時点) | 運用益(利益) |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 1,440万円 | 約3,545万円 | 約2,105万円 |
| 30歳 | 1,260万円 | 約2,741万円 | 約1,481万円 |
| 35歳 | 1,080万円 | 約2,082万円 | 約1,002万円 |
※シミュレーションは年利4%で一定のリターンがあると仮定したものであり、実際の結果を保証するものではありません。
※NISA制度を利用すれば運用益には税金がかかりませんが、利用しない場合は約20%の税金がかかり、利益が目減りすることに注意が必要です。
まとめ

投資信託とETF、それぞれに良さがあるが、初心者には投資信託のほうが始めやすく、長期での資産形成に向いている。
とはいえ、ETFのように配当金が欲しい、リアルタイムに取引したいという人にはETFも十分選択肢になります。
どちらを選ぶにしても、
-
無理のない範囲で始めること
-
余剰資金で投資すること
-
投資は自己責任で行うこと
この3つを大切に、資産形成していこう!
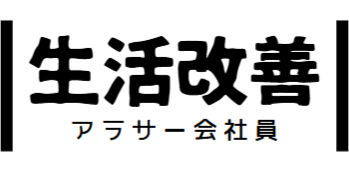
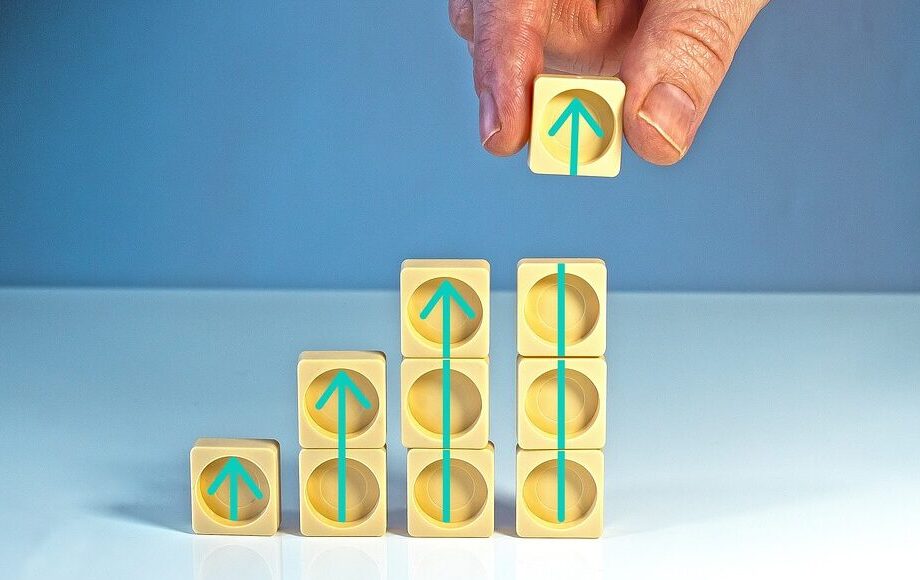


コメント